目次
ご遺骨をどうしよう・・・お墓?自宅保管?
江戸幕府の政策であるの寺檀制度より「ご遺骨はお墓に納骨するもの」と慣習化してきたため、「ご遺骨の自宅保管」と聞くと、戸惑われる方もいらっしゃいます。
しかし、近年、お墓離れが進み「慣習に縛られたくない」「お墓が無い」「故人と離れたくない」「お墓は故人の死生観と合わない」等の理由から、ご遺骨をご自宅にて保管されている方は実際に増えてきています。
今までは「自宅にご遺骨を保管しているよ」と気軽に話す人はあまりいませんでしたが、ご遺骨を除菌・粉骨するという保存方法や、デザイン性豊かな自宅墓(お骨壺)が次々と登場してきていることから、ご遺骨の自宅保管はお墓以外の選択肢として浸透していくと考えられます。
ご遺骨:自宅保管への戸惑い
「自宅保管へ踏み切れない」ご遺骨の自宅保管へ戸惑いを感じる要素

- ご遺骨の扱い方が分からない
- 四十九日に納骨しないと宗教上問題がある気がする。
- 成仏出来ない気がする
- 法律上違法にならないか心配
- 綺麗に保管できる気がしない
- ご遺骨に魂が宿っていそう
これは、ご遺骨の自宅保管に踏み切れない要素としてよく耳のする内容です。
~ 宗教上の問題はないのか? ~
四十九日納骨 / 成仏
《四十九日に納骨を行う理由は?》
寺院墓地などのお墓への納骨は、一般的に四十九日法要の後を目安とし行われます。
日本の仏教の考えとしては、死者の霊は死後7日ごとに冥土の裁きを受けるとされています。そして四十九日に最後の審判が下され、その魂の行き先が決められます。仏教上の考えから四十九日を「目安」として納骨することが慣習として行われてきました。
明確にその日と定められている訳では無く、四十九日を目安としている為、実際にはお坊さんや親族の予定を摺り合わせてご納骨の日時が決まります。また、お墓が用意できない等の理由により、四十九日を目安に納骨できないときは一周忌、3回忌等の回忌法要を目安に行われる事も多くあります。
日本仏教では、四十九日の納骨(埋葬)は目安として行われてはいる。
また、法的には納骨の期日に決まりはない。
《 納骨しないと「成仏」しないのか? 》
先に述べたように、日本仏教の考えでは、故人の霊は亡くなってから四十九日に冥土の裁きを受け、魂の行き先が決まります。従って「成仏しない」=「死者の魂が現世をさまよい続ける(行き先が決まらない)」ことは四十九日以降はありません。
また、浄土真宗では、故人の霊がこの世をさまようという考えはなく、阿弥陀如来にお縋りるカタチで南無阿弥陀仏と唱えていれば、死の直後に極楽往生するとされています。
日本仏教上、「納骨(埋葬)しないと成仏できない」は間違い
~ 慣習上、生じる問題 ~
お墓のあり方や埋葬方法は、そのときの時代背景や考え方が反映され変化を遂げてきました。現代のお墓の形は、「火葬」が進むにつれ変化を遂げた物で、その前は「両墓制」と言い、一故人に対し「埋め墓」「詣り墓」の二つのお墓がありました。今日でもお墓や埋葬方法は変化を遂げ、納骨堂や海洋散骨、自宅墓等、多様性を見せています。
慣習もその時々の時代背景により変化致します。祭祀承継者がいなかったり、後に残される物への負担を軽減するため、期限付きのお墓や、宗教・宗派を問わないお墓が望まれたり、散骨を望む方も多くいらっしゃいます。
慣習で問題になるのは、今までの行いを守りたいと思う側と、新しい形へ適用しようとする者との考えの違いから摩擦が生まれるところにあります。
今までの慣習に従わず、葬儀をせずに直葬という形を取ったことにより、継承したお墓へ納骨することをお寺から拒まれる事もあります。「後々は菩提寺の墓へ納骨するかも知れない」という方は、慣習にも重きを置いて行動する必要があるかも知れません。
自宅墓を選択する場合でも、宗教的行為に沿って行動することは可能かと思います。その場合は親族やお寺へご相談することをお勧め致します。
菩提寺の「お墓に入れないぞ」は法的に有効かどうか https://news.goo.ne.jp/article/oshietewat/life/oshietewat-be13d08e102c8d4658e1e9ecf85f7ef7.html
~ 法律上の問題は? ~
法律上、ご遺骨を「何時までに埋葬しなくてはいけない」という記載は無く、期限はありません。
捨てたり、勝手に埋めたりという行為は違法行為となりますが、ご自宅で保管することは違法行為とはなりません。
しかし、承継してくれる方がいない場合、最終的に散骨にするのか、お墓に埋葬するのか決めて準備しておく必要があります。
自宅墓の承継について
祭祀承継者など、ご遺骨の所有権を有する人が自宅墓を承継することは可能です。
ご遺骨は都営霊園や寺院墓地など、許可された場所以外では埋葬できません。庭に埋めたり、所有する山へ埋めたりと、ご遺骨は許可されていない場所に埋めると罰せられます。
承継してくれる方がいる場合も、承継者が困ることが無いよう最終的にはどの様に扱って欲しいか、話し合い、準備しておくことをお勧め致します。
結論
自宅墓として、ご自宅でご遺骨の保管をすることは法律上、日本仏教上問題はありません。慣習上不都合がある場合や、最終的に寺院墓地に納骨する場合は、お寺や親族の方とお話しされることをお勧め致します。
◆日本仏教では、四十九日法要に納骨をしなくてはいけないという宗教上の決まりは無い。
◆納骨(埋葬)しなくては「成仏出来ない」ということはない。
◆法律上、納骨の期限は無く、自宅に保管しても違法では無い
従来墓のネガティブ イメージ

- 維持管理にお金がかかる
- お墓は高額
- お墓は更地に戻す費用も高額
- 墓参りで遠出が大変
- 祭祀・儀式など、宗教的行事に対応出来ない
- お墓を承継する人がいない
- 供養への宗教的縛りがある
では何故、自宅保管をせずお墓への埋葬が四十九日を目安とし、行われるのでしょうか?

◆宗教上の問題は無いのか ◆法律上の問題は無いのか?
葬儀、法要、納骨等は慣習として祭祀承継者へ引き継がれてきました。今はその慣習も時代の流れに簡略化されてきており、今のライフスタイルに添った物へと変化してきています。日本のお墓文化は土葬から火葬(埋葬)へと変化を遂げ、亡骸はお墓へという考えが一般的でした。自宅保管は「宗教」「法律」というより、慣習として
日本のお墓文化は土葬から火葬(埋葬)へと変化を遂げ、亡骸はお墓へという考えが一般的でした。火葬技術の向上もあり、ご遺骨はお骨壺に収まる時は
では何故、自宅保管という考えが薄かったのでしょうか
何か悪いことが起こると、霊のせいとされ、不吉なもの
良くない
ネット環境が普及するまでは、情報が限られる中、葬儀、埋葬は慣習を中心に行われてきました。
「四十九日に納骨しなくてはいけない」「納骨しないと成仏できない」という考えに縛られる必要は無い。
相手方の信仰心や供養の気持ちを蔑ろにすることなく、話し合いを重ね対応していく必要があります。
自宅墓=ご遺骨の自宅保管は違法でも、仏教上問題があるわけでは無い
《ご遺骨を自宅に置くと不幸が生じるのか?》
信仰心が無いのに、祭祀承継者としてお墓を引き継ぎ、慣習に従い祭祀を執り行う事に疑問を感じる方もいらっしゃいます。とは言え、四十九日を目安としてしまうと葬儀から納骨まで疑問を改善する余裕はありません。
火葬が普及する前は、山林など、人里離れた場所に人は亡くなると埋葬されてきました。日本の起源を考えても、数十万年前から土葬が繰り返されてきており、今生活している地下深くに、かつて埋葬されたご遺骨が眠っていたとしてもおかしくはありません。霊的現象を個人でどう捉えるかは人それぞれですが、ご遺骨が人を不幸にするという根拠はないと考えます。
宗教や法律を知らないが為に、慣習として「四十九日に納骨しなくてはいけない」「納骨しないと成仏できない」など強迫観念に駆られ
埋葬方法・お墓選びは慎重に
《信仰心が無い場合、墓じまいや改葬を考えている場合の対処法》
信仰心が無い場合でも、慣習に流されるカタチで葬儀やお墓への納骨が四十九日を目安とし行われる事があります。
葬儀・宗教・慣習に捕らわれない場合
直送だと菩提寺に納骨を断られてしまうケースがあります。
直葬が菩提寺と関係のないところで執り行われるからです。
通常であれば、通夜や葬儀などで僧侶が読経をします。直葬の場合は通夜も葬儀もなく、火葬のみで宗教儀式が執り行われません。そのため、宗教観を大事にする菩提寺の僧侶によっては直葬を快く思わない場合もあります。菩提寺に納骨を断られるリスクは、直葬の最大のデメリットといえるでしょう。
葬儀をお考えの場合
最近ではご遺骨の行き場が定まら無い場合や、お墓に納骨することに寂しさを感じてしまうという理由から、ご自宅でご遺骨を保管されている方も多くいらっしゃいます。
火葬埋葬が発達する以前、土葬を基本としていたころのお墓のあり方で、一故人に対し二つの墓を作ることから両墓制と呼ばれていました。遺体の埋葬墓地のことを「埋め墓(葬地)」、墓参のための墓地を「詣り墓(まいりはか、祭地)」と言いますが、民俗学における文献を見ても、「遺骨はさほど顧みられることはなかった」とされており、
参考資料:火葬と両墓制の仏教民俗学 及び火葬墓制の仏教民俗学的研究 霊根観の行方
ご遺骨を埋蔵できる場所は、国営・都営・市営霊園等の行政が運営する墓所、寺院墓地、民間霊園等が挙げられます。
近年では今のライフスタイルに沿った宗教宗派を問わないお墓の需要が多くなってきてはいるものの、今までお墓を承継するという考えが生活に根付いていた事もあり、代々お世話になったお寺に「ご遺骨を納める」という流れが当たり前になっています。
49日法要までに納骨を進められる
- 宗教上の考え方から四十九日にお墓に納めなければならない。
- 最終的には法律に則った形で埋葬・散骨をしなくてはならない。
但し、最終的には法律に則った形での埋葬か、散骨をすることとなりますので、埋葬、散骨などの正しい知識が執拗となします。
ご遺骨をご自宅で保管することに法律上では何の問題もございません。
- お墓は高くて買えない
- お墓を受け継ぐ人がいない
- 残された家族に負担を掛けたくない
「成仏する」とは本来、人が悟りの境地に達し成仏となることを示しますが、日本では独自の死生観と仏教が結び付き、死後極楽に生まれ変わるという意味で使われるようになりました。逆に「成仏できない」とは死者の霊魂が現世をさまよい続けると言う意味で使われることがあります。
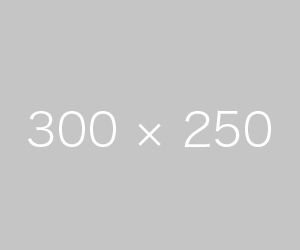
コメント